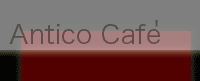

|
|
|
寓話・黄昏・サウダード ―宮崎次郎の異化作用― |
|
寓話とは教訓や処世訓・風刺を動物など別の事柄に置きかえて物語ったものをいう。人間を揶揄したり風刺したりするには最も効果的な手法だ。古くは「イソップ物語」、現代ではジョージ・オーウェルの「動物農場」がその代表といえよう。 1990年代の宮崎次郎の作品が寓話的といわれるのも、鳥や山羊といった人間に馴染みある動物が服を着て登場し、ペテン師や行商人と取引きする現場が描かれているから。孵化しかけた、もはや商品価値のない卵を売りつける行商人とその売買をめぐって駆け引きを演じたり、妖しげなカフェでペテン師の話を疑い深げに聞いている鳥顔の人物がその代表。同じ画面の中に納まったとき、中世ヨーロッパ風の衣装をまとったひとびとは単なる人物としてでなく、やはり何かを揶揄する象徴的な存在として浮かび上がる。画面のなかの別世界で繰り広げられる物語が、私たちが生きる現実世界の裏側のカラクリを鏡像となって垣間見せる。異化作用の一つの手法だ。一度その寓話の世界に引き込またものは、たとえ画面から目を背け、再び自分の世界に戻ったとしてもこれまでの自身の身辺を同じ視線で見ることはできない。 平穏な生活のなかに突然あらわれた、不安を喚起する異人たち。ジプシーや旅芸人といったいわゆる流れ者たちは、平常の生活のなかに不穏な空気を持ち込む。閉じた街の外部からこっそり侵入し、エキゾチックなリズムで街人を惑わす。見世物小屋、マジシャンのテーブル、移動オルゴール。好奇の目を集める舞台は、黄昏どき、昼の労働の時間から夜の安息の時間へと移行するその隙間に開かれる。境界線上の不安定な時間が、旅芸人たちの稼ぎどきだ。 人は何かに幻惑されることを切望しながら、しかし日常を裏返しにされ、破壊されることを好まない。別世界が運び込んでくる畏れと恐れ。それが宮崎作品が引き起こす異化作用(Verfremdungseffekt)の源である。 97年の渡仏を契機に、その作風は一つの転回をはかる。ジプシーや行商人は姿を消し、それにかわってカフェに集まる紳士淑女、サーカスの象や玩具が画面を飾る。そこに流れるのは哀愁であり、過去を思い出したときに感じる郷愁である。 それを画家はサウダードの一語で呼び表す。サウダード(Saudade)とはポルトガル語で郷愁や哀愁を意味する言葉。画家は言う。 「それは、そこはかとない後悔の思い、誰かに会いたいという切なる願い、友情や悲しくも甘味の漂った記憶など・・・つまり人生のある地点から自身の歩んできた道程を振りかえったときに沸き起こる情感のことだと思う」 一年間、異国の地フランスで異人として過ごした彼が得たもの。それは一般旅行者が経験するようなカルチャーショックではなかった。自ら放浪の旅芸人的な生活を送ったことで、別世界は畏れるものでも、恐れるものでもなくなってしまった。むしろ日常のある時間に、ふっと過去の体験が呼びさまされる、誰にでもある哀愁に満ちた時間を描くこと。それによって再び日々の生活が平穏に過ぎ行くことを願った絵画を彼は求める。 画家が幼少時に刻んだ思い出のひとつは、多忙な両親にかわってお手伝いさんに連れて行ってもらったサーカスまでの光景。 「黄昏に近い時刻、小石を蹴りながら進む道の左右に露店の燈りが点々と灯り始め、天幕が楽曲の音とともに徐々に近づいてくるその光景は、未だ空き地がよく目立ち、アスファルトの鋪装も珍しかった昭和三十年代から四十年代の初頭にかけての空気を止めどもなく甦らせてくれる・・・」 作品の中でも昼から夜へ移行する黄昏の時間は、寓話的な、別世界を開く時間から過去への郷愁が開かれるサウダードの時間へと転回した。部屋の窓辺にたたずむ男たちも、カフェで知り合った男と女も、ガストハウス(旅宿)の前を歩く婦人も、まだ明るい空に低く上った月の下で、ふっと自分の歩いてきた道を振り返る。 思い出とは写真や記念品といった物体として存在する思い出の品ではない。また記憶のなかにある固定された体験でもなければ、過ぎ去った時間、失われた生活のことでもない。それは思い出すこと、想起するというその時々の現在に一瞬だけその人とその周辺に湧き上がる充実した意識のことである。その一瞬だけ人は外界から切り離され、自分自身が別世界の主人公となる。宮崎次郎はこうしてサウダードという言葉であらされるもう一つの異化作用を手に入れた。 恐れと不安を垣間見せることから、一瞬の充実した空気を描くことへの転向。それは別世界からの帰還を果たした画家・宮崎次郎の今をあらわしている。 西村孝俊 |
|
宮崎次郎画集「サォウダード」 出版「求龍堂」 |
ここに掲載する絵画、写真、イラストおよび文書等は、許諾無しに使用することはできません。