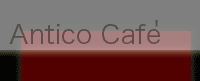

|
|
|
|
|
|
|
|
 夕焼けの曲芸師 油彩 15F サーカス 人は誰しも、或る程度の年齢に達したとき、不図、或る心の傾向に関し、自分は何うしてこの様な事象に心引かれてしまうのであろう、と淡々と考えてみる機会があるものではないだろうか。そうして、つらつらと考えてみるうちに、その原因が、案外、子供の頃の思い出と可成り強く結び付いている事に気が付いて、一寸意外の感に打たれる場合もあるのではないだろうか。 私にとってサーカスは、最も重要な絵の主題の一つである。そうして、この私にとって掛け替えの無いモチーフもまた、私の遥か幼少の頃の記憶と相呼応している。まだ小学生だった頃の或る日、私は、自分の住む町にサーカスの一座がやって来る事を知り、両親に、この興行に連れて行って呉れるようせがんだ。しかし、仕事で多忙な両親は御手伝いさんに頼んで、私をサーカスに連れて行って貰う事にしたのだった。 |
|
仄暗い暮方の光の中で、道の両側には露店の燈(あかり)が点々と灯り始め、私は御手伝いさんに手を引かれ乍ら、賑やかな楽曲の鳴り響いて来る大きな天幕(テント)の方へと向かって行った。あのとき買って貰った綿飴の匂いを今でも、何かの折に不図思い出す事がある。 獅子(ライオン)が火の輪を潜ったり、象が後ろ脚丈で立ち上がってみせたり、美女が駆け抜ける白馬の上で様々な芸をしてみせたり、そんな一つ一つの演し物に私は好奇の目を見張っていた。ピエロが同じ失敗を何度も繰り返すのに笑いこけ、綱渡りや空中鞦韆(ぶらんこ)を見上げつつ手に汗を握っていた。 けれども、こうした華やかな演し物の全てが終り、やがて天幕(テント)から出て、多くの人々に混って御手伝いさんと帰路に付いているとき、私は不図、何だか寂しい様な心持ちになった。その寂しさが何であるかは無論当時の幼かった私には分からなかった。そうしてそれが、別れを前提として出会う旅芸人たちが持つ彼ら独特の匂いである事に私が気が付いたのは、ずっと後になってからの事だった。 ※年間3ヶ月をパリで過ごす洋画家・宮崎次郎さんがパリの街と人々への愛着を綴る連載。全12回。 みやざき・じろう 1961年埼玉県生まれ。95年昭和会賞受賞。 97年文化庁派遣芸術家在外研修員として渡仏。 現在、無所属。 11月に銀座・ごらくギャラリーにて個展開催予定。 |
ここに掲載する絵画、写真、イラストおよび文書等は、許諾無しに使用することはできません。