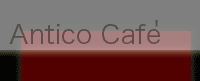

 
  
  
   
  |
この十年間を振り返ってみて、自らの画業を一つ一つ点検してみると、我ながら、様々な変化を体験して来たものだとつくづく思わせられる。 先ずは、DERACINE(デラシネ)。DERACINE(デラシネ)とはフランス語で根なし草と云う意味である。青春時代以来、自らの存在の落ち着く場所を探し求める私の内面は、思索と旅と云う形を取って日常と非日常の中で具体化され、それらは全て、私の絵画作品の中で結晶化した。そのDERACINE(デラシネ)の環境をベースにした作品群を纏(まと)めて世に問うたのが、もうかれこれ十年以上の昔である。 それから、在外研修員として巴里に渡ったのが97年、翌年はフランスでサッカーのワールドカップが催された年で、その前後、街は随分と賑やかだったのが思い返される。あの時分、私は巴里で思い掛けない出会いをした。それは、自らの過去、遠い忘却の彼方に消え掛かっていた少年の日の思い出との再会であった。 クリシー広場の傍(そば)に天幕を張る、ジプシーの移動サーカスのロマネスを見物に行ったその日、私は、何か、遠い、然し懐かしい時に呼び寄せられるのを感じ、軈(やが)てそれが、小学生の頃、お手伝いさんに連れられて見に行ったキグレ大サーカスの思い出であることに気が付き、この仄(ほの)かな記憶が、実は、私の中で以外な程重要な位置を占めている事に気が付くに至った。 旅人として、さすらい続けて来た私。その私と、旅を日常とする移動サーカスの人々が漂わせている人生の悲哀。この時分から、私は、自ら根なし草(デラシネ)的な境涯を求め、遠く故郷を離れ、異郷の地を好んで歩く生き方から、その反対の方向、望郷の念、自らの来し方を懐かしむ思いに捕われ出したと云える。 巴里で得た収穫を、私は、99年、SAUDADE(サウダード:ポルトガル語で、様々な懐旧の情を表現する多義語)のサブタイトルの下に展示した。これらの作品群は、私のそれまでの作品から今日のそれへと向う転換点となった。それ以降の作品には、広い意味で、自らの過去を振り返る事、味わう事から、人生の深みを噛み締める姿勢が貫かれている。 時は過ぎ、世の中の空気は変わっても、変わらないもの、この変わらないものに突き動かされて画家は、藝術家は仕事をする。この変わらぬもの、永遠の息吹の様なものが、絵筆を通して画布(カンバス)に塗り込められて行く。 若き日の屈折した思い、観念的な思索は、恐らくは自然な形で、無駄な部分が削ぎ落された。そうしてその私の内面の余白に、新たな、永遠の生命が盛られて行く。私の描く薄明り、そこには黎明(れいめい)の希望が籠(こ)められている。人間の、藝術の、そしてあらゆる誠意ある生命にとってのESPOIR(エスポワール)が。 2006.5 宮崎 次郎
|
ここに掲載する絵画、写真、イラストおよび文書等は、許諾無しに使用することはできません。