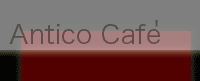

|
|
|
|
|
雲はその日の天候を反映するかのように、茜色に染まっている。それは、その日の私たちの気持ちを写すかのように、赤から赤紫へさらに濃い青紫へと移りゆっくりと西の山脈をおおってゆくのを見ることがある。陽が山の向こう側へ帰ってゆく頃には、空は群青色の幕をおろしはじめて、白い三日月があるのに気がつくのであった。 秋の日の ギオロンの ためいきの 身にしみて ひたぶるに うら悲し。 夕暮れは秋の日がよく似合いふと思い出されるのであった。フランスの詩人ヴェルレーヌの詩「落葉」の一節であるが、上田敏の『海潮音』であまりにもなじみ深い詩ではある。この詩は「秋の歌」とも題されて、現代も数々の詩人に訳されて愛唱されている。 宮崎次郎さんの風景は、ほとんどが夕ぐれ時で日常の喧噪が静まり非日常の入口が開く頃なのであった。そして開いた窓から見える風景でもあるのだった。あたかも劇場の幕のようなビロードの厚地のカーテンがしつらえている。そして部屋にはテーブルが置かれて人たちが囲んでいるのである。 窓からの風景を描いた絵画は、ルネッサンス期からみられ、現代でも割合多く描かれてはいる構図である。フランスに在住していた版画家の長谷川潔をはじめ、イギリスの画家のベン・ニコルソンなどにみられるのである。ただそこには、テーブルの上に器など静物が配置され、カーテン布が揺れていてその土地の風景が描かれているという構図であった。 宮崎さんの窓は、巴里のサンジェルマン・デ・プレにでもある建物なのだろうか。開け放した窓から見る風景のなかの建物の窓も、そろそろ明かりの付きそうな時刻である。夕ぐれのカフェ・ドゥ・マゴで濃いめの香りのよい珈琲をゆっくりとすすりながらぼんやりとながめている時の窓のようであった。 絵には、しばしば詩人が登場する。遠くを視ている詩人のようである。詩人たちも、このようなカフェで珈琲を飲んだのではないだろうか。町の小路をちょっと曲がると小さな図書館などもあり、よく朗読会がひらかれたりするのである。もうずいぶん前になるが、朗読した時がよみがえるのであった。 鐘のおとに 胸ふたぎ 色かへて 涙ぐむ 過ぎし日の おもひでや。 鳥が詩人に詩の実を渡しているのだった。鳥は天の使いともいわれていて天から詩の実を渡しにきたのだろう。それは青い実であったり赤い実であったりするのはなぜだろうか。 というように一枚一枚を見ていくとどの絵にも物語がこめられている気がするのである。私が最も引きつけられた「青い魚」の絵を見る。 赤いカーテンのある部屋には、大きなテーブルが置かれて三人の人たちがいる。テーブルには皿に盛られた青い魚があるのだった。ひとりは詩人で葡萄酒にほほをそめて瞑想のなかでうっとりとして、ひとりは画家でたばこをふかし何かを待つかのように遠くを見て、ひとりは芸人で道化帽をかぶって曲芸の後の大喝采を思いだしているのだった。窓辺にはひときわ大きな壷があり、大輪の花々が華やかにいけられている。大輪の花は芸術家たちの夢の開花を未来を暗示しているかのようである。 また青い魚は、三人の芸術家の完成された作品のように輝いているではないか。私たちの悲しい記憶を嬉しい記憶を再生しているように、ほりおこすのだった。そうなのであった。埋もれてしまったかのような気持ちがうずくのはきまって夕ぐれであったのだ。 登場人物たちは、帽子をかぶり外套を着て首まきをしている。マフラーやスカーフともいい私たちになじみ深いものであるが、あえて首まきといいたくなるような細長い布を、首に幾重にもまいているのである。色の数だけある彩色筆で鮮やかに創りだされたもう一枚の外套のように、あるいは言葉の嵐から守るように。道化の装飾衿にみられるように人格の一部分になっているのだった。これなら、いつでも記憶の旅にさえ出られるのだ。 宮崎さんの住んでいる浦和の街は緑の多い町で中山道にそって家々が並ぶかつての宿場町である。詩人立原道造のヒヤシンス・ハウスの建つ別所沼があり狛犬ならぬ狛兎のいる調(つき)神社の境内では、お祭りにはサーカスや見世物小屋などがでるのだった。そうして、小学校の向い側に中学校と高等学校が隣りあっていたりする町で、詩人や画家が散歩しているのに出会うところである。学生時代まで過ごした町で、夕ぐれになると明かりの付く家々があり、私にとっても居心地のいい懐かしい場所なのである。 宮崎さんの窓からは、マジシャンが手品でだす精妙な手技で、懐かしい哀感をだしてみせるのであった。長い上着のポケットから、いくつもの時代を自在にだしてみせるのである。私たちは誰よりも誰よりも自分の記憶を懐かしみ愛でていいのである。それは、倖せを引き寄せ、見えないものをも感じさせる気配の窓ともいうべき窓であるといえよう。窓で演じられる物語によって私たちは倖せな呼吸をすることができるのである。 |
|
宮崎次郎画集「サォウダード」 出版「求龍堂」 |
ここに掲載する絵画、写真、イラストおよび文書等は、許諾無しに使用することはできません。