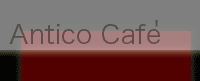サウダード(Saudade)とはポルトガル語で郷愁や哀愁を意味する言葉といわれるが、その多義的な言葉の性格から人によってさまざまなニュアンスを含んで用いられる。一人旅の孤独感を表すこともあれば、祭りが終わった後に感じるあの寂しく空しい気持ちを表したりもする。
サウダード(Saudade)とはポルトガル語で郷愁や哀愁を意味する言葉といわれるが、その多義的な言葉の性格から人によってさまざまなニュアンスを含んで用いられる。一人旅の孤独感を表すこともあれば、祭りが終わった後に感じるあの寂しく空しい気持ちを表したりもする。
洋画家・宮崎次郎さんは数年前からこの言葉を制作のテーマとしている。
「それは、そこはかとない後悔の思い、誰かに会いたいという切なる願い、友情や悲しくも甘味の漂った記憶など・・・つまり人生のある地点から自信の歩んできた道程を振りかえったときに沸き起こる情感のことだと思うんです」
人物、花、建物のある風景などどれを描いても画面から漂う物悲しさは、いずれも作家の心に巣食った一つのこの言葉から導かれている。
もともと宮崎さんはシュール系の画家として知られていた。テンペラの技法を取り混ぜながら、人間が擬人化された鳥や山羊と商取引をする場面や、服をまとった動物たちの楽団の興行風景など、中世ヨーロッパ的な場面で展開される違和感と物語性に満ちた作風が特徴だった。
個展を中心に活動しながら、95年には昭和会賞を受賞。しかし、作家の中で作品の中で形作る世界は徐々に変化。それが決定的になったのが文化庁在外研修員としてのパリ滞在から帰国してからのことだったという。
「シュール的な絵画で、自分は世の中の別の面というか、人間を通常とは別の角度から見ることでそれを揶揄したり皮肉をこめて表現してきました。若い頃はそれでやってきましたが、しかし、それは非常にエネルギーが要ることなんですね。歳を重ねていくと、そうした力ずくの作品というのは難しくなってくる。精神を切り詰めたり懸命に何かに立ち向かうだけでなく、むしろ今、自分が描きたい作品を描きたくなってきたわけです」
パリではモンスリ公園の見えるパリ大学国際都市のアトリエで制作していた。15〜16世紀のロマネスクの祭壇彫刻、聖母子像などの模写をしながら、自分の制作も続けていた。アトリエを拠点に、オペラを見たり、映画を見たり、また様々な人種がダイナミックに集散するパリという豊饒な環境の中で、日本人としてのものを作る必然性がはっきり見えてきた。そして直接画家の想像力を刺激する経験に出会うことになる。それがサウダードの一つの象徴的実体となるサーカスだったという。
|
 |
「クリシー広場の近くにテントを張るロマネスというジプシーサーカスはよく見ました。軽技や綱渡りなどのいわゆる旅芸人のサーカスの雰囲気をもっているんですが、それはスペクタクル型の大規模なものではなくて、芸人の悲哀や放浪し移動する者の哀愁を感じさせる独特の舞台なんです」
宮崎さんがサーカスに見い出したのは、ジプシーという異文化の特殊な存在の哀愁だが、それは自身の記憶のなかにある懐かしくも今は失われてしまった時間を連想させた。それは展覧会に寄せた一文では次のように語られている。
「・・・黄昏に近い時刻、小石を蹴りながら進む道の左右に露店の燈りが点々と灯り始め、天幕が楽曲の音とともに徐々に近づいてくるその光景は、未だ空き地がよく目立ち、アスファルトの鋪装も珍しかった昭和三十年代から四十年代の初頭にかけての空気を止めどもなく甦らせてくれる・・・」
 目の前のジプシーサーカスが、子供のときに連れて行ってもらったキグレ大サーカスの空気を想起させる。そのとき過去は再現可能な記憶としてではなく、一度通り過ぎると再び訪れることのできない街のように、別の世界として現れる。
目の前のジプシーサーカスが、子供のときに連れて行ってもらったキグレ大サーカスの空気を想起させる。そのとき過去は再現可能な記憶としてではなく、一度通り過ぎると再び訪れることのできない街のように、別の世界として現れる。
シュールレアリスムの別世界が人を不安にさせたり違和感を引き起こしたりする非現実の世界であるのに対して、サーカスが想起させる別世界はむしろ楽しさと淋しさを折り合わせた懐かしい感じを呼び覚ます別世界といえる。
画家はそれを自らの絵画作品で再現する。サーカスだけでなく、画家が描く人物にも、花にも、建物にも、見る人に別の世界へと誘う力が宿り、それが人々に同じ情感を感じさせる。それが宮崎さんのいうサウダードであり、達成されるべき作品の内実なのである。




|