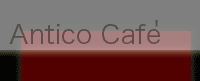手品師、サーカス、旅芸人、故郷を離れ、根無し草(デラシネ)のように彷徨する人々の姿を描き、寓意とメタファーに満ちた濃密な物語世界を紡ぎ出す洋画家、宮崎次郎。
手品師、サーカス、旅芸人、故郷を離れ、根無し草(デラシネ)のように彷徨する人々の姿を描き、寓意とメタファーに満ちた濃密な物語世界を紡ぎ出す洋画家、宮崎次郎。
「僕は青空をあからさまに描くことができないんです。見世物小屋のビロードのカーテンの隙間からこっそりと覗く、とでも言えばいいのかな」
ここ近年、個展のテーマとしているのは、Saudade(サウダード)というポルトガル語である。デラシネからサウダードへ。
「サウダードというのは、境界といった意味ですが、この言葉は実に多様な使われ方をするのです。国境などの地理的な概念を表すこともあれば、夜と昼の境などの時間的な概念を言うことも。また望郷の思いや、様々な情念を含んだ記憶、想念を飲み込んだ多義語なんです。自分の仕事と響き合うところがある言葉なんですね」
パリ風景を描いた作品でも、描かれた時刻を特定することは難しい。それは黄昏なのか夜明けなのか、すべては鑑賞者にまかされている。ただ、画家の心情としては、その昏さの果てに、何らかの黎明、希望といったものを込めているとも語る。
今回の個展は、、とりわけサーカスのイメージ、記憶、想念に影響されている。パリ滞在時代に足繁く通った四区、グラン・ブールヴァールの傍の常設サーカス「シルク・ディヴェール」(冬のサーカス)、あるいは、クリシー広場近くの露地に天幕を張り興業を打っているジプシー・サーカスの、ちょっと胸が熱くなるようなロマネスクの味わい。空中ブランコ、軽技、綱渡り、曲馬・・・。
|
 |
「僕にとってサーカスは、パリ時代の思い出以前に、幼い頃、お手伝いさんに手を引かれて見に行った近所のサーカスの光景にルーツがあるんです。まだ昭和が若かった頃の雰囲気、空気が詰まっていた。露店の灯りが灯りはじめる黄昏時、歩みを進めるごとに、独特の楽曲が流れる中、次第に近づいてくる天幕のことを思い出します。いわば自分の中にあるサーカスですね」
埼玉の医師の家に生まれ、当然継ぐはずの家業に早くから背を向け、オペラや映画などへの情熱と無為の日々が表裏となっていた若い年。一つの画面に描かれたイメージそれ自体が完結した物語をかたちづくっているようなシュルレアリスム系の作品を描いていたボヘミアン気質の時代。昭和会賞を受賞して思いがけず洋画壇の寵児となり、文化庁派遣で渡仏、異国の地で画家としてのプライドを確認して帰国した、それぞれの時代を経て、自らの人生がかつてもっていたすべての可能性を懐かしみつつ、未来へ向かおうとすること。
「40歳を迎えた年の瀬に、そのことの記憶を手繰り寄せながら、いま自分の創造の過程も熟しつつあるような気がしています」


|